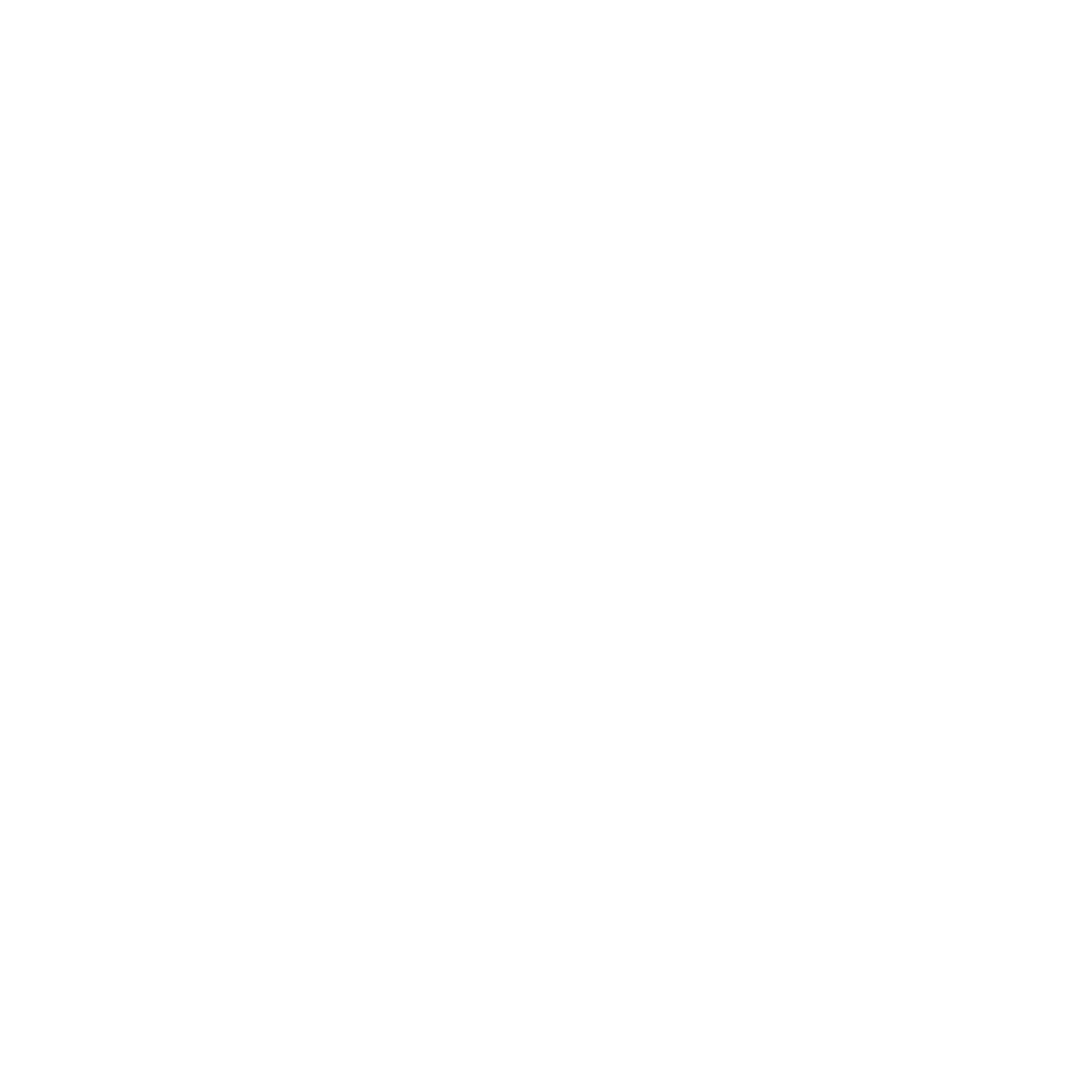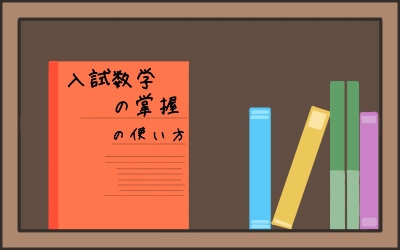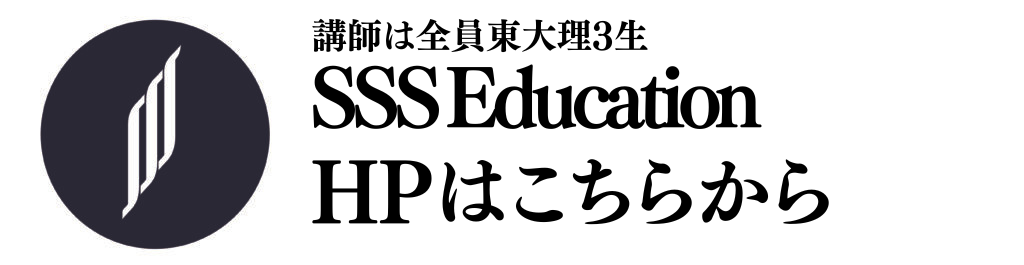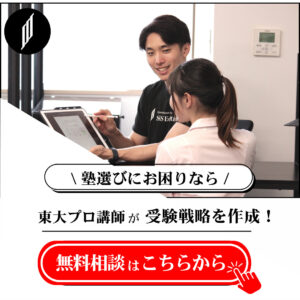SSS Education とは…
「国内最高峰の教育を、全国へ。」の理念をもとに、2022年に設立。講師は全員東大理3生で、経歴が様々な講師が在籍。現役生、浪人生、再受験生まであらゆる生徒の指導経験が豊富で難関大学、医学部へ多くの合格者を輩出。SSS Educationの提供する教育プログラムは、才能やセンスを必要とせず、誰でも努力次第で国内トップレベルの能力を身につけることができます。対面生、地方の生徒(オンライン)でもしっかり学べるカリキュラムを構築し展開している。
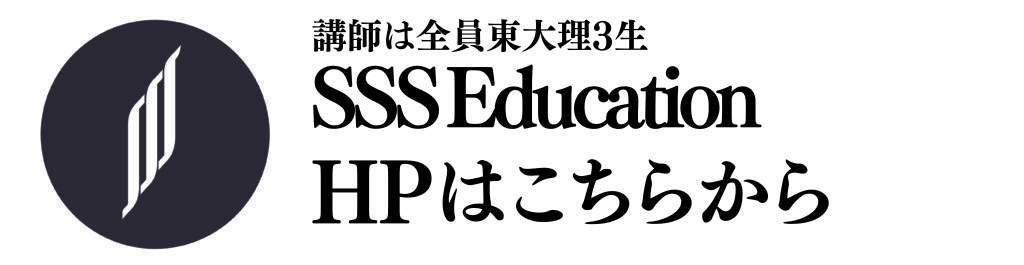

・目次
入試数学の掌握とは? ページ数と問題数 レベル 目安の所要時間 学習の進め方 本書の特徴 本書の進め方 おすすめポイント入試数学の掌握とは?
ここでは入試数学の掌握を紹介していきたいと思います。
入試数学の掌握は、テーマ別演習①総論編、テーマ別演習②各論練磨編、テーマ別演習③各論実践編の全3冊からなります。
3冊とも表紙に、「君の数学力を理Ⅲ・京医・阪医合格レベルに導く究極の指南書」と書いているようにとても難易度の高い本です。
ページ数と問題数
入試数学の掌握の各テキストのページ数と問題数は以下のようになっています。
テーマ別演習①総論編(全214p)
| 単元 | ページ数 | 問題数 |
|---|---|---|
| theme1 全称命題の扱い | 73 | 例題11問+確認問題14問 |
| theme2 存在命題の扱い | 53 | 例題8問+確認問題11問 |
テーマ別演習②各論練磨編(全276p)
| 単元 | ページ数 | 問題数 |
|---|---|---|
| theme3 通過領域の極意 | 97 | 例題6問+確認問題7問 |
| theme4 論証武器の選択 | 51 | 例題5問+確認問題問13問 |
| theme5 一意性の示し方 | 33 | 例題4問+確認問題問2問 |
テーマ別演習③各論実践編(全276p)
| 単元 | ページ数 | 合計問題数 |
|---|---|---|
| theme6 解析武器の選択 | 75 | 例題7問+確認問題15問 |
| theme7 ものさしの定め方 | 33 | 例題4問+確認問題7問 |
| theme8 誘導の意義を考える | 59 | 例題6問+確認問題6問 |
レベル
3冊とも表紙に、「君の数学力を理Ⅲ・京医・阪医合格レベルに導く究極の指南書」と書いているようにとても難易度の高い本です。
扱っている問題も東大・京大・阪大の過去問がメインで、レベル的にはとても高いと言えます。
しかし、問題の解答解説がどの問題集よりも丁寧であり、受験数学の最頻出事項をテーマにしていることもあって、表紙の東大、京大、阪大の医学部に限らず、東大理Ⅰ、理Ⅱやその他国立医学部を志望する全ての人におすすめできます。
特に、解答解説がしっかりしているため、大学への数学の「新数学演習」や大学の過去問で挫折してしまった人であっても、一度手に取って問題を解き、解答解説を読むことはとてもおすすめできます。
難しい問題の解答解説を理解はできるが、いざ模試では上手く解法選択ができない人にとてもお勧めできます。
一方で、まだ青チャートレベルもやっていない、大学への数学の1対1対応をやっている途中など、まだ演習を詰めていないならお勧めできません。
本の中でも、陥りやすい回答などが紹介されているので、何回か国立大の過去問、もしくはそのレベルの問題を解いたことがあることが必須だと思います。
目安の所要時間
レベルが非常に高い本ですが、テーマに沿って問題を精選していて、かつ、問題の分析を丁寧にすることで、解答に至るまでの背景をとても詳しく説明しています。
テーマ内で例題と例題同士のつながりや違い、さらには例題と確認問題のつながりを意識して解くことが非常に重要になってきます。
よって、1日1テーマを目標にして勉強するのがいいでしょう。
1日1テーマに集中して勉強すると、テーマの全体像やテーマ内で使われている問題同士のつながりが理解できると思います。
実際は1テーマでも問題数10問ほどの違いがあるので、1テーマに1〜2日かけてたとして、3冊を2〜3週間でまず1周、全て終わらせましょう。
この本の解答解説はとにかく丁寧なので、問題から解答までの流れを頭の中ですっと再現できるように、復習を何回もするべきです。
1回目の復習は1〜2週間で、2回目の復習は1週間で、、と何回も復習して流れをマスターしましょう。
1ヶ月半で、復習込みで3〜4周できたら素晴らしいです。
学習の進め方
目安の所要時間のところで、1日1テーマを目標にしましたが、では1テーマ内の問題をどのように進めていけばいいでしょうか。
まず、他の本にはない、この本の特徴を知ることが必要です。
本書の特徴
この本では、一般の参考書・問題集と違い、問題文と解答の間、つまり「なんでその解答になったのか?」「どうしてその方針になると気づけるのか」を読者に分かるように問題を咀嚼して伝えてくれています。
問題と解答作成までの間を言語化して伝えることが、どれだけ大事かというと、「今まで読者がやってきた解き方は、実際どのような理由でその解き方を選択すべきなのか」「模試の解答解説は分かるのに、本番では解けない理由はなぜか」ということに自覚的になれるからです。
数学が安定してできる人とできない人の違いは、「雰囲気でなんとなくあの問題に似てるから、それの解き方と同じでいいんじゃないか」ということを繰り返しているかどうかです。
この本は、その雰囲気解きの癖を治してくれる本と言えるでしょう。
本書の進め方
さて、肝心の進め方ですが、雰囲気解きの癖を治すためにはただただ読むだけではその癖は治りません!!
まずはテーマの例題を解きましょう、正直、時間は多くはかけなくていいので、1問25分の制限はつけておきましょう。
終わったら例題の解説を理解しながら読んでいきます。
この時、自分の解き方やどこで詰まったかを意識しながら読んでいくことで、なぜ解けなかったのかをより意識することができると思います。
また、読んでいくと前に書いてあった文章を忘れがちです。
ですから、問題文から解答までの間をつなげるために、逐一、問題文と解説を行き来することが非常に重要になってきます。
雰囲気で読み進めていくのではなく、必ず納得しながら読みましょう。
解説を読むときは、「問題やテーマのポイント」と「それに対する数式処理・考え方」という2軸で捉えるとわかりやすいと思います。
例題の解説と解答を読み終わったら、問題文を見ながら、今までの流れを再現することが大事です。
解答を作成するというよりも、解答を作成するまでの道のりを整理しながら「だから、解答はこうなる」というのを意識して、紙にポイントを書き出すといいです。
これができたら、テーマの類題があるので、例題で学んだ方針選択を意識して、解きましょう。これも25分と決めるといいです。
解けても、解けなくても、類題の解答と例題の解答解説をもう一度照らし合わせながら、解答までの流れを自分の中に落とし込みましょう。
1テーマに5〜10問ほどの例題があります、例題1問を解説を読んで深めていくのと同時に、全ての例題を解き終わったら、テーマ内のつながりや違い、共通点も確認する必要があります。
例題の解説をより深めるためにも1テーマが終わった時には、そこで扱われた例題の問題をもう一回全て眺めながら、解答作成までの道のり(問題やテーマのポイントとそれに対する対応)を自分でなぞれるかを必ず確認して下さい。
さらに言えば、3冊を通して、問題文と解答の間を考える癖をつけるようにしましょう!
模試の解答解説で「なぜこの解答になったのか」がわからなくなったら、自分なりに問題文と解答の間を埋めるように考える癖をつけるといいです。
「こうやって解くんだ、ふーん」ではなく、「なんでこの解法だって分かるんだ!もっと、入試数学の掌握ぐらい丁寧に書いてくれ!」というスタンスで不親切な解答解説にくってかかるべきです。
3冊を丁寧に取り組むことで、問題文やテーマを分析することが大事で、問題文での着眼点やあるテーマの着眼点などに気づけるようになる(ないし気付けなくても、少なくとも意識するようにはなる)と思います。
入試数学の掌握ではどのように考えていたかなと意識しながら、模試や過去問、その他難問の分析を自分なりにしていくことが大切です。
おすすめポイント
今までを振り返って、この本のおすすめポイントを簡単にまとめます。
- 問題と解答の間にある「どうしてこの方針なの?」「この解答ではどうしてダメなの?」を詳しく解説していること
- 入試に頻出のテーマを深掘りしていること
- テーマごとに幾つかの例題を紹介していて、解法選択の根拠を比較できること
- 類題は例題で学んだ解答までの道のりを自分で再現するにはちょうど良いこと
などがこの本のいいところです。
特に、問題と解答作成までの間を埋めるように言語化してを示していることは、他の問題集や参考書にはないとても素晴らしいポイントだと思います。
数学の伸び悩みの最大の原因とも言える「雰囲気解き」の癖を直し、根拠を持って解答を作成するためのとても良い教材だと思います。
SSS Educationって?
SSS Educationは「国内最高峰の教育を、全国へ」の理念をもとに2022年6月30日に創業しました。
講師には東大理3生のみを採用しており、質の高い教育を届けています。
SSS Educationの教育内容は、才能やセンスに頼らない設計にし、
誰しもが 努力をすれば国内屈指の実力を体得出来るカリキュラムを開発しております。
正しい知識を持った講師が一人ひとりに合わせた適切な学習計画を構築し、効率を最大限に高めていきます。
あなたの努力の方向性を正し、合格へと導きます。
2025年も東大理科三類3名の合格。
※合格者情報は随時更新予定
2024年合格実績…(40名中)
東京大学 – 理科三類(2名中2名合格),理科二類,理科一類(2名)
国立医学部 – 10名 , 私立医学部 – 8名
40名中医学部合格者20名、東大、一橋大学を含む難関大学16名の合格者
※SSS Educationでは入塾制限を設けておりません。全ての方にご利用いただけます。