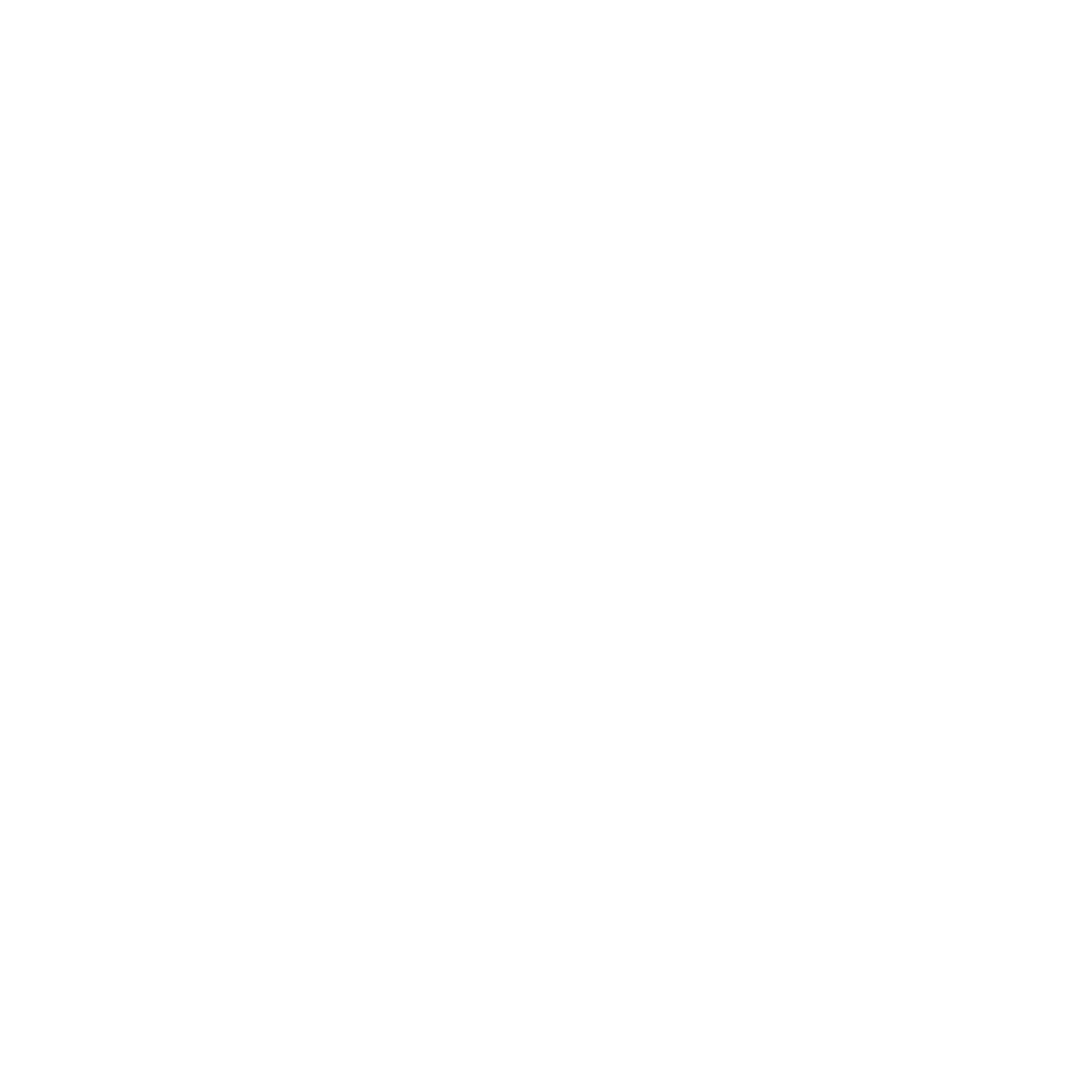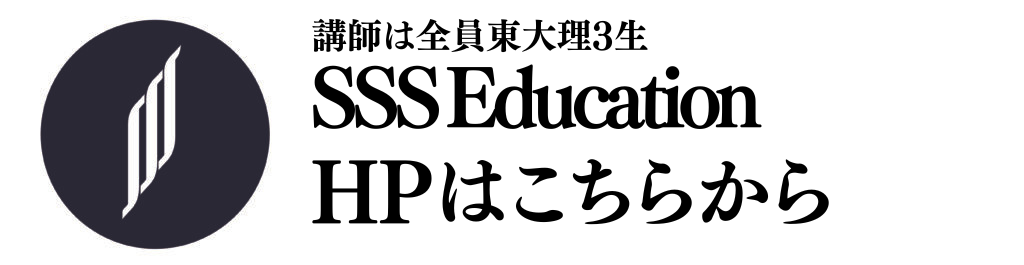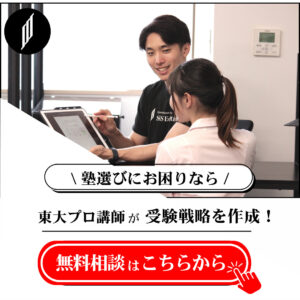SSS Education とは…
「国内最高峰の教育を、全国へ。」の理念をもとに、2022年に設立。講師は全員東大理3生で、経歴が様々な講師が在籍。現役生、浪人生、再受験生まであらゆる生徒の指導経験が豊富で難関大学、医学部へ多くの合格者を輩出。SSS Educationの提供する教育プログラムは、才能やセンスを必要とせず、誰でも努力次第で国内トップレベルの能力を身につけることができます。対面生、地方の生徒(オンライン)でもしっかり学べるカリキュラムを構築し展開している。
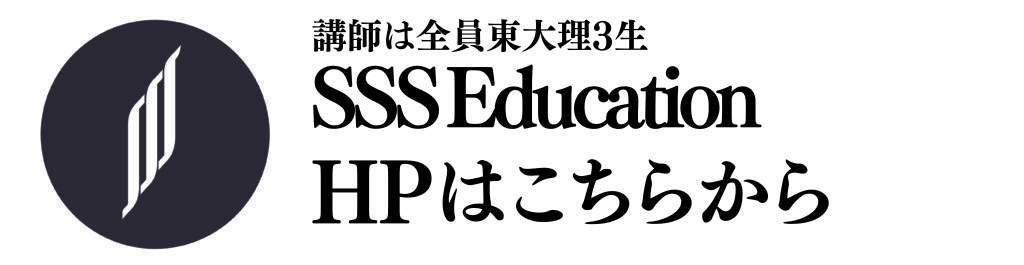

目次
〜はじめに〜 数学上達に必要な姿勢
以前の投稿でも、今回でも、何度も同じことを述べてしまうかもしれませんが
前回の投稿はこちらから!
数学の問題をただ解けばそれで数学の勉強になると思っていませんか?そのような勉強を続けていても、一問解いたら一問できるようになるだけで、決して効率的な勉強法とは言えませんよね。
それでは、入試問題が解けるか解けないかが、それまでにその問題をたまたま見たことがあるかないかにかかってしまいます。
それを防ぐために大事なことは、1を聞いて10を知ろうとする姿勢です。もっと難しく言えば、一つ一つの問題からきちんと一般的な法則を抽出し、それらの法則を体系化し整理することが大事になります。
簡単にできることではないかもしれませんが、だからこそ重要なんです。
いろんな問題で使えそうな形で道具(公式)を覚えて、さらに道具同士をきちんと関連付けることが大切ですね。
という話でしたね。さて、チャート式は上記のような数学の「ホンモノの学習の仕方」においてどのように活用するのがよいのでしょうか、早速覗いていきましょう!
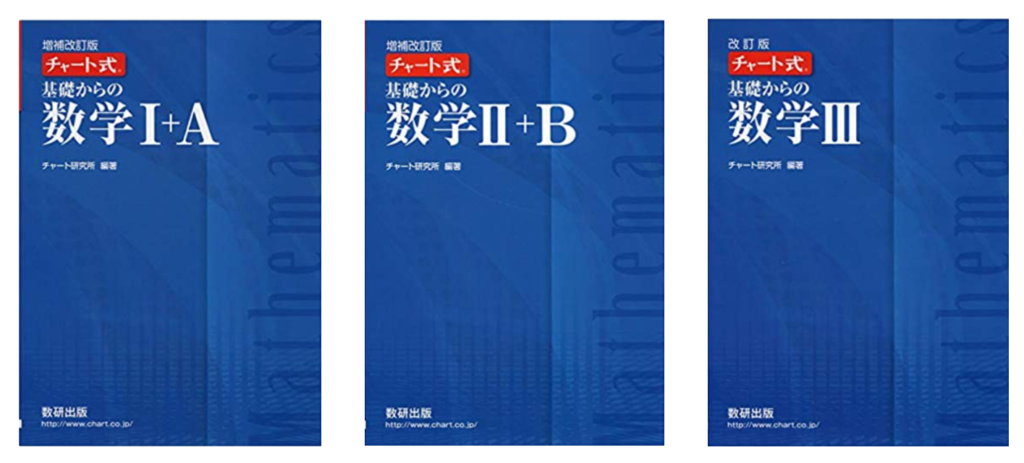
長所①:難しいことに踏み込みすぎない優しさ
総ページ数や問題数の情報を書きます。
一つ一つの問題からきちんと一般的な法則を抽出し、それらの法則を体系化し整理することが大事になると冒頭で述べましたが、初学の時点から重箱の隅をつつくように受験数学を完璧にカバーした体系を練り上げるのは困難ですよね。チャート式の問題集では、「初学のうちはまだそこまで手を伸ばさなくてもいいかな」という部分と「これはさすがにできてほしい」という部分にきちんと線引きがなされています。
長所②:「点」を学ぶに最適な範囲の広さと問題量
対象となる学年や目的を書きます。
一般化や体系化を行うためには、そもそもまずは1つ1つの道具が身についていることが大切です。チャート式では、①で述べたように、初学者が身につけるにちょうどいい塩梅の範囲がカバーされています。そしてその中の1つ1つの道具が確実に身につくような構成になっています。
具体的には、「例題の解説」→「〇〇なときは△△するという形式のマニュアルの提示」→「練習問題」という流れが各ページで展開されており、1つ1つの道具がきちんと可視化されており、さらにそれをきちんと手を動かして豊富な分量の問題を解くことで習熟できる仕組みになっています。
最終的には点と点を線で結んでいく作業が必要な数学の学習において、点を習熟するにふさわしい形態となっています。
短所:「線」の学習が難しい
例題の流れや解説の丁寧さなど特徴を書きます。
このブログは参考書をべた褒めするものではありません。基礎を極めてきた我々東大理3の者が教育的観点から参考書を本音で斬る企画です!正直に短所も述べておきましょう。
数学では点と点を結んで線をつなぐことが大切だと先ほど述べました。たしかにチャート式は1つ1つの道具については、「〇〇なときは△△する」といった形できちんと可視化されており、さらにはそれを練習するための問題量が豊富です。
しかしながら、チャート式では、そうした点どうしを結ぶ線は見にくいです。もちろん初学者でも点どうしを結んで線をつないでいく「一般化・体系化」の作業はできてほしいところが本音なのですが、現実的には実際難しいものです。世の参考書では本来そうした点と点のつなぎ方を生徒が自主学習できるようなものであるべきにもかかわらずそれが提示されていないのが現状です。チャート式もその例に漏れず、チャート式だけをやって点と点がつながってきちんと数学の全体像が見えました、という声を聞くことはなかなかなく、難しいものです。
「点の学習」という入門の意味では最適な参考書ですが、それをゴールだと思ってはならず、「線の学習」という意味ではよりしっかりとした参考書が必要そうですね。
(しっかりとした参考書:市販でならば前回紹介のNALがおすすめです。さらに重箱の隅をつつくまで受験数学をすべて網羅した教材が見たい方はこちらまでどうぞ。)
ここまでのまとめ
先生自身がどんな使い方をしたかを書きます。
特徴まとめ!
「点の学習」という入門の意味では最適な参考書ですが、それをゴールだと思ってはならず、「線の学習」という意味ではよりしっかりとした参考書が必要そうですね。
(しっかりとした参考書:市販でならば前回紹介のNALがおすすめです。さらに重箱の隅をつつくまで受験数学をすべて網羅した教材が見たい方はこちらまでどうぞ。)
| 難しいことに踏み込みすぎない | まずは初学者が学習するべき事柄に絞ってある。 |
| 点を学ぶには有効 | 1つ1つの問題について、もって帰るべきメッセージが明確である。 |
| 線を学ぶには不足 | 問題間ごとのつながりが見えづらい。 |
学習計画の道標
参考書の内容を習得するためには、計画的な継続と反復が鍵になります。故に、各参考書のページ数や章の数、問題数をおさえておくことは勉強計画作成に非常に重要になります。下表にある程度の指標を共有しておきますので、勉強計画を立てる際にはご参考になさってください!
| 分野 | 例題 | 練習 | exercises | 総合演習 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 177 | 177 | 130 | 28 | 512 |
| A | 137 | 137 | 107 | 25 | 406 |
| Ⅱ | 242 | 242 | 153 | 38 | 675 |
| B | 167 | 167 | 110 | 28 | 472 |
| Ⅲ | 271 | 271 | 240 | 59 | 841 |
| 合計 | 994 | 994 | 740 | 178 | 2906 |
学習のコツ:数学初心者
「初めて数 1+A, 2+B, 3 を勉強する」「学校でやった分野もあるけど全然わかっていない」といった方は、以下の3ポイントを意識して取り組みましょう。
- まずは、星1★~星3★★★ から!
頭から完璧に参考書を完成させたい!という気持ちはわかります。しかし、どれだけ数学ができる人でも、最初はみんなものすごく簡単な問題から始めているのです。。完璧にしたい気持ちはわかりますが 、まずは地道な理解な養い、全体像をぼんやりと見えることになることが肝要です!
よって、まずは星1★~星3★★★から取り組んでいき、それ以上の星4や5の問題はちらっと見てわからなかった潔く飛ばしましょう! - 3分詰まったら解説を見て、それを学習する姿勢で!
自分で解かないと意味がないと思い込んで、全部の問題にたくさん時間をかけている人もいるかもしれませんが、勉強の目的や現状のステップに応じてかける時間は変わってきます。
初学者としてチャート式を用いる場合は、そもそも道具をインプットしている段階です。今はまだ頭の中に何も入っていなくて、それをきちんとした形にして入れていこうという段階です。そのような状態で「思考力をつけよう」などといっていくら時間をかけても…ですね。
分からないものは潔く諦めて、謙虚に解説を読んでそこから学びを得るという学習方法が良いと思います! - 問題ごとの比較を意識しよう!
初学者は道具の暗記が必要だし、まずはそこから始めるべきだともいいましたが、本当にそれだけを無限にリピートしていてもいつまでも上達しません。「ぼく/わたしチャート5周したよ!」なんて言っているお友達は周りにいませんか?そういう人は要注意です!もちろん、何か学ぶべきポイントを明確にして、わけがあってそうしているのならば止めはしませんが、ただ問題集を何周もして解いてるだけで数学の力が養われるわけではありません。
初学者のひとは中級者になるためにすることは、問題ごとの比較を行うという姿勢を身につけることです。最初は雑でもかまいません。「あ、この問題のやり方とあの問題のやり方同じじゃん!」とか「似たような問題なのにこっちの問題とあっちの問題でやっていることが全然違うなぁ…」とか、そういった発見をする習慣をつけましょう!ただし、まだ知識が少ない段階でそうした発見を完全に解決するのは難しいので、深入りしすぎないように注意しましょう。まずは意識づけ!
学習のコツ:数学中級者向け
「一通り学習を終えたけど、まだ共通テストでも6割7割を超えない」「中堅レベルの記述模試でも全然できない」といった方は、以下のポイントを参考にしてください。
多く!速く!丁寧に!解く
多くの受験生の数学が伸び悩む3大理由は、①演習量不足②計算練習不足③情報整理ルーチンの脆弱性です。
ギクッっとした方も多いんじゃないんでしょうか。しかし、安心してください。その対策は非常にシンプルです。その概要を以下に記します。
①演習量不足
👉練習問題まで必ず取り組みましょう。
②計算練習不足
👉各問題に必ず制限時間を設けましょう。なるべく暗算で飛ばせる部分は飛ばしましょう。
③情報整理ルーチンの脆弱性
👉式の各項のまとまりを意識する、大事な式を一箇所にまとめる、必ず方向性を決めて式変形を行う、などを徹底しましょう。
練習問題を、例題を解いた次の日にずらして行うなど、記憶への定着も良くなる一工夫もご参考になさってください。
短所のところで、「点」だけの学習になりがちとはのべたものの、そこに載っている「点」をきちんと習熟しただけでも十分な演習量や計算量はカバーできます。たとえ仮に情報整理ができずに「線」が形成されていなかったとしても、チャートに載っている「点」だけで共通テストならば満点は必ず取れます。「自分は初学者・中級者」とか「チャートでは線がつながらない…」とかいう言い訳をするくらいなら覚悟を決めて「点」をマスターしましょう。中級者から上級者になるためにはそのくらいの覚悟が必要とされると思います。
一通り学習を終えて共通テスト8割は安定してとれる」「GMARCH レベルなら確実に合格点が取れる」といった方は、以下のポイントを参考にしてください。
星3★★★までは頭で方針を考えればOK
上級者の網羅系参考書の使い方は「ツブシ」です。すなわち、苦手な部分がないか精査し、その部分を再確認し埋めることが重要になります。そして、簡単な問題に時間をかけず、難しい問題を考える時間にあてるべきです。
よって、星3★★★以下の比較的簡単な例題については、問題文を読み頭の中で方針を考え(あわよくば暗算で解ききり)、ある程度固まったら解説を読んで確認するといった感じで、パパッと飛ばしていくことが大事になります。
星4★★★★以上は、素早く解き、確実に答えを合わせる。
上級者でも演習が完璧な人は殆どおらず、網羅系参考書に計算されるような典型題が意外と時間がかかったり、計算が煩雑になり計算ミスをしたりして苦戦することは少なくありません。よって、星4★★★★以上の問題については、実戦の如く時間を測り確実に満点を取りに行く姿勢で取り組みましょう。目安時間は各問 10-15 分の間で考えると良いと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?同じ参考書でも、最適な使い方は学習者の現状の実力でも変わってきますが、決してそれだけではなく、得意・苦手の性向(2次関数はできるけど場合の数ができない、マーク模試だと解けるけど記述式だと全然できないといった傾向)や考え方の癖によって、使い方は変わってきます。
しかし、自分にどんな勉強法があっているのかは、なかなか自分ではわからないものですよね。自分の考え方の癖なんて自分で気付けるはずが…
そのような受験のお悩みを抱えている生徒はごまんといます。
受験生の時間は限られていて、非常に貴重です。非効率な方法で続けてしまった学習法は、その貴重な時間を効率悪く使ってしまうことになり、その時間決して返って来ません。ですので、受験に悩まれる方は東大理3生に相談することで、一日でも早く学習方法の課題を解決し、より多くの時間を効率高く活用できるようにしましょう!
SSS Educationって?
SSS Educationは「国内最高峰の教育を、全国へ」の理念をもとに2022年6月30日に創業しました。
講師には東大理3生のみを採用しており、質の高い教育を届けています。
SSS Educationの教育内容は、才能やセンスに頼らない設計にし、
誰しもが 努力をすれば国内屈指の実力を体得出来るカリキュラムを開発しております。
正しい知識を持った講師が一人ひとりに合わせた適切な学習計画を構築し、効率を最大限に高めていきます。
あなたの努力の方向性を正し、合格へと導きます。
2025年も東大理科三類3名の合格。
※合格者情報は随時更新予定
2024年合格実績…(40名中)
東京大学 – 理科三類(2名中2名合格),理科二類,理科一類(2名)
国立医学部 – 10名 , 私立医学部 – 8名
40名中医学部合格者20名、東大、一橋大学を含む難関大学16名の合格者
※SSS Educationでは入塾制限を設けておりません。全ての方にご利用いただけます。